子どもが科学や自然、生き物に興味を持ち始めたとき、どんな学びの場を選びますか? 自宅学習や図鑑、動画も良いけれど、やっぱり本物に触れる体験は格別です。
今回は、我が家が年長から小学校1年生まで実際に参加して大満足だった「早稲田こどもフィールドサイエンス教室」について、体験談を交えて詳しくご紹介します。
まず・・・自然教室とサイエンス教室、どちらを選ぶ?
科学に興味のある幼児・小学生向けの教室には大きく2種類あります。
- 実際の自然の中で活動を行う「自然教室」(→今回記事)
- 室内で実験や工作を通じて学ぶ「サイエンス教室」(→関連記事:【理科好きキッズ比較レビュー】栄光サイエンスラボ・ベネッセサイエンス教室)
我が家でも、子どもが科学や生き物に興味を持ったタイミングで、いくつかの教室を見学・体験してきました。結果として選んだのが、「早稲田こどもフィールドサイエンス教室」でした。
早稲田こどもフィールドサイエンス教室とは?
この教室は、年間プログラム制で、年7回程度のフィールドワークが用意されています。
- 場所:新宿または池袋集合・解散。実習地へバスで移動。
- 内容:毎回異なるフィールド(山、川、海など)で自然と科学をテーマにした活動を行う。
- 費用:年間一括払い(フィールドワーク1回あたりの費用で換算すると約24,200円(入会費等別途))
年長から小学生まで。レベルに応じた学び
我が家の子は年長から小1までの2年間通いました。幼児クラス(年長)は、自然を五感で体験しながら学ぶ構成で、小学校受験で出てくるようなテーマ(例:昆虫の特徴、水辺の生き物、など)も、体験として身につけられました。
小学生クラスは、学年別に指導内容や内容の深さを調整しつつも合同催行。本格的なフィールドワークで上の学年の学びに触れることで良い刺激にもなりました。
特に印象的だったのは、「目で見て、触れて、感じる」ことを何より大切にしている点。図鑑や動画では到底味わえない、本物の自然に飛び込む体験ができます。
本格的なフィールドワークと専門家による指導
毎回訪れる実習地は、普通の家族旅行やキャンプではまず行けないような本格的な自然環境。しかも、講師陣は専門分野をもつプロフェッショナル。
- 川や磯での生き物観察
- 山での地質や植物の探究
- 化石探しや標本づくり
こうした体験を、専門家から直接学べる機会は、東京都心の子どもたちにとっては非常に貴重です。
家でも学びが続く工夫
活動の前には、実習の狙いや実習地についての詳しい説明と、予習としてあらかじめ実習にまつわる課題に取り組むプリントが配信され、課題は実習当日に持参しバス車内で全体に共有・発表しあいます。
また、実習終了後には実習内容を振り返る復習プリントも用意されており、どんな体験をしたかを親子で話し合いながら内容を振り返り知識を定着させ体験を「知識」として定着させる工夫もされています。
実際に見つけた標本や化石などを持ち帰れるため、子どもにとっては学びの“宝物”になります。
コスパは? 高い?安い?
費用面だけ見ると、決して安くはないと感じるかもしれません。
ですが、
- 毎回あたり朝から夕方までの長時間の実習
- 本格的なフィールドワーク
- 専門家の指導
- 復習プリントや標本付き
これらを含めて考えると、都市型のサイエンス教室よりも「体験の密度」が高く、むしろ割安と感じました。
アウトドアが苦手な家庭にもおすすめ!
我が家のように、
- 親がアウトドア苦手(虫が無理、暑いのも寒いのも無理)
- キャンプや登山に自力で連れていけない
という家庭でも、子どもが安全に、しかも質の高い自然体験を得られるという点で、この教室は本当にありがたかったです。
まとめ
「自然が好き」「生き物が好き」「図鑑を眺めるのが好き」な幼児や小学生は、ぜひ体験してほしい教室です。年度はじめには体験授業もやっているのでぜひチェックしてみてください。
机の上だけでは育たない「生きた知識」と「自然へのリスペクト」。それを五感で体感できるのが、「早稲田こどもフィールドサイエンス教室」だと思っています。
関連記事:【理科好きキッズ比較レビュー】栄光サイエンスラボ・ベネッセサイエンス教室
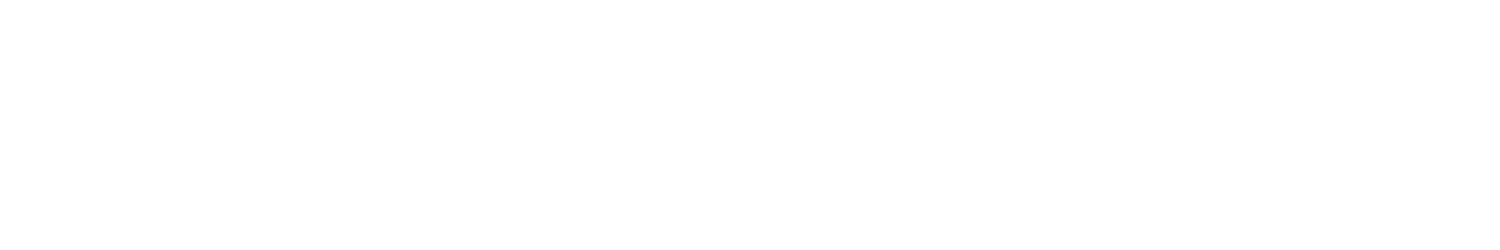


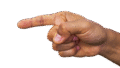

コメント