「子どもが読書好きに育ってほしい」──そう願う親御さんは多いはずです。
わが家では、子どもが生まれた頃から、子どもを読書好きにするための環境を意識的に作ってきました。そうすると、生後半年から保育園に通い始めた頃には、先生から「読み聞かせが大好きですね」「絵本を一人でページをめくって眺めています」と言われるようになっていました。小学生になった今では、暇さえあれば本棚の前にいて、出かける時には必ず数冊の本を持っていく“読書好き”に育ちました。
今回は、そんなわが家で実際に試してよかった「子どもを読書好きにする環境づくり」について5つをご紹介します。
▼関連記事【4つのステップ】子どもを読書好きにする読み聞かせのコツ
子どもを読書好きにする方法① リビングに本を置く・おもちゃはしまう
子どもを読書好きにするには、物理的な距離を縮めることがいちばんの近道。
家族がいちばん長く過ごすリビングに本棚を置いています。そして、おもちゃ類は全て子どもの部屋に収納するようにし、取り出すのが面倒なようにしています。
我が家では、リビングの物語、科学、図鑑、学習漫画などをカテゴリー別で200冊程度置いています。

知り合いのご家庭では、リビングだけでなく、廊下や階段、トイレなど、いろんなところに少しずつ本を置いている、という工夫をされている方もいらっしゃいました。
いつも本が近くにあり、他の魅力的おもちゃやゲームがしまってある状態であれば、隙間時間に本に手を伸ばす習慣がつきます。
子どもを読書好きにする方法② 本屋さんに寄ることを“習慣”にする
さらに、お出かけをするときなどに、スーパーやコンビニのように“ついでに立ち寄る場所”として、できるだけ書店に立ち寄ることを習慣にしています。
誰かと待ち合わせするときは書店。次の予定まで時間があったら書店。「近くに本屋さんあるからちょっと行ってみようー」と気軽に行くことで、本との距離がグッと近づきます。
本当は図書館に行きたいところなのですが、我が家は図書館から少し距離があるので、お出かけのたびに立ち寄るのは難しいです。本屋さんは図書館よりもたくさんあちこちにありますし、最近では本屋さんでも座って読めるようにベンチが置いてあるところなども増えていますね。また、本屋だと、新しい本や注目されている本が一目でわかるので、本との新しい出合いにうってつけです。
子どもを読書好きにする方法③ おもちゃやゲームではなく“本”を与える
わが家では、おもちゃは誕生日やクリスマスだけと決めています。(どうしても欲しい場合は、自分のお金(お年玉)で買うというスタイル)その代わり、本は定期的に購入しています。
本屋に立ち寄った際に子どもが選んだ本を購入するするだけでなく、子どもの興味のありそうな本や季節行事に関連するテーマの本を見繕って購入しては、本棚にそっと入れておきます。
例えば、わが家では、2〜3歳の頃から恐竜や生き物、自然科学系の本に関心を持ち始めたので、そのあたりのジャンルは特に充実しています。ちなみに、恐竜や生き物、自然科学系に興味を持つようになったきっかけは、 かはく【国立科学博物館】の科学絵本シリーズにハマったことでした。
▶︎関連記事 【理系脳が育つ】「かがくのお話25」シリーズは何歳から?魅力と活用法!
また、年齢的に「ちょっと難しいかな?」と思う本でも、本棚に並べておくと、意外と手に取って眺めることがあります。
大人向けの文庫本や物語なども、背表紙のタイトルや表紙の絵に反応して「これ何?」と聞いてくることも。
本選びの参考には、日本絵本賞や、本屋大賞の受賞作品もおすすめです。選書に悩んだとき、読みやすく感動的な作品が多く見つかります。
また、我が家では年中の頃から小学生新聞を購読していますが、そこで紹介されている本を購入することも。
▶︎関連記事 【幼児から習慣化!】子どもの視野を広げる小学生新聞のすすめ!
また、以下の本には教育専門家のおすすめブックリストが付属されているので、我が家ではそのリストから新しい本を選ぶことも多いです。
子どもを読書好きにするために親ができること 筑波大学付属小学校国語科教諭 白坂洋一
子どもを本好きにする10の秘訣 花まる学習会 高濱正伸 平沼純
“おもちゃ”ではなく“本”を贈る選択は、子どもの未来に残る贈り物だと思います。
子どもを読書好きにする方法④ 子どもの本を、親も一人で読む
よく、親が普段から読書している姿を見せるといい、と言われますが、我が家では親の私たちは恥ずかしながらさほど読書週間がありませんでした。そこで意識したのは、子どもの本を読むようにすること。
時間がある時は、私も子どもの本を読みながら一人でくつろいでいます。
すると、子どもが「何読んでるの?」「それね、こういう話なんだよ」と嬉しそうに近寄って話しかけてくれて、読み聞かせが始まったり、同じシリーズの別の本を一人で自然と読み始めたり。
「お母さん(お父さん)も自分の読んでいる本に興味を持ってくれてる!」
そんな嬉しさから、さらに読書が好きになってくれているように思います。
子どもを読書好きにする方法⑤ 本の内容でクイズを出し合う
読んだ内容をただ話すだけでなく、クイズ形式にして出し合うと、楽しさがぐんとアップします。
たとえば、「幸せの青い鳥を探して旅をしたのは?」「(伝記で読んだ)グレースケリーはどこの国に嫁いだ?」など、ゆるい感じでOK。
子どもも得意げに答えてくれるし、記憶にも残りやすいように思います。
小学生に上がってからは、自分で読んで知った知識をクイズに出してくれますが、全く答えられないことが多いです。得意顔で教えてくれます。
本の内容から会話を広げることで、「本って面白い!」「誰かと共有するともっと楽しい!」という気持ちを育てたいです。
まとめ|“本があるのが当たり前”の家庭が、いちばん強い
読書が好きな子に育てたいとき、「読書しなさい」と強制しても、なかなかうまくいかないもの。
それよりも、本がいつも近くにある、親も楽しんでいる、話題にできる──そんな環境や雰囲気づくりこそが、一番の近道なのかもしれません。
本との自然な距離感を、これからも大切にしていきたいです。
▼関連記事【4つのステップ】子どもを読書好きにする読み聞かせのコツ
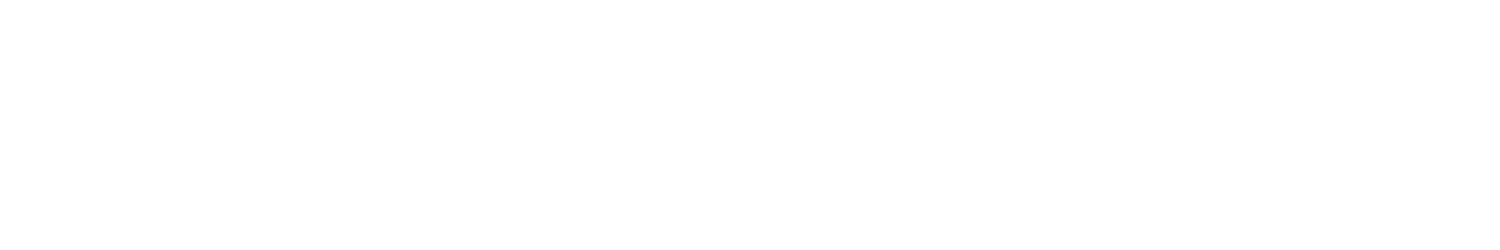





コメント