「子どもには読書好きになってほしい」──そんな想いから、絵本の読み聞かせを大切にしているご家庭も多いと思います。
しかし、絵本を大量に読み聞かせても、なかなか自分から本を読むようにならない、というご家庭も多いのではないでしょうか。
実は、読み聞かせと“自分で本を読む”ことの間には、大きなステップがあります。受動的に聞く読み聞かせと、能動的に読む読書。この差を埋めていく読み聞かせのコツがとても大切なのです。
読み聞かせは“量”より“質と方法”。この記事では、我が家の実体験をもとに、子どもを読書好きに導く読み聞かせのコツの「4つのステップ」をご紹介します。
▼関連記事【親ができる5つの工夫】子どもを読書好きにする環境づくり
読書好きにする読み聞かせのコツ ① 本に自然に手が伸びる環境づくり
わが家では、「毎日○冊読む」などのノルマは設けず、絵本を身近に置くことを大切にしてきました。おもちゃと同じように絵本がすぐそばにあると、子どもは自然と手を伸ばします。興味を持ったタイミングで一緒に読んで楽しむ──その積み重ねが「本は楽しいもの」という感覚につながっていきます。
また、テレビや動画の視聴は極力控えていました。絵本が「いちばん面白い遊び」と感じてほしかったからです。
読み聞かせる際も、ゆっくり抑揚をつけて読むのではなく、普段の会話と同じテンポで読むよう意識していました。子ども自身が自由に感じ、想像する時間を大切にしたかったからです。
▼参考記事【親ができる5つの工夫】子どもを読書好きにする環境づくり
読書好きにする読み聞かせのコツ ② 耳でお話を味わう体験を増やす
子どもが言葉を理解し始めた頃から、わが家では「耳で聴く読書」も意識して取り入れてきました。絵本の読み聞かせに加えて、文章だけのストーリーを耳から楽しむ機会を増やしていったのです。
というのも、読書は単に文字を読めるようになればいいというものではありません。絵のないページに書かれた文章を読み、その内容を頭の中で想像し、自分なりの情景や登場人物の姿を思い描く──そんな“イメージする力”が求められるのです。
その力の土台になるのが、「耳で聴いて、想像する」経験だと感じています。
子どもが一人で遊んでいる時や車での移動中などに、昔話や童話の朗読CDや音源を、音楽のように流していました。最初は何となく聞き流しているだけでしたが、いつの間にか話の続きを知りたがったり、同じお話を繰り返しリクエストしたりするように。
また、寝る前のひとときには、私が即興で創作した物語や昔話をアレンジしたお話を聞かせることも。たとえば「今日はおもちちゃんが宇宙へ行ったお話にしようか」などと、子ども自身が主人公になったファンタジー仕立てのお話にすると大喜び。話の途中で「つづきはこうなるんじゃない?」と自分で続きを考え出すこともあり、想像の世界を自由に広げている様子が見てとれました。
こうした「耳で聴いてイメージする」体験は、子どもにとって絵や映像に頼らずに物語を楽しむ大切なステップです。そしてそれは、絵本から活字の本へ、そして“自分で読む読書”へとつながる準備にもなると感じています。
読書好きにする読み聞かせのコツ③ 児童書の読み聞かせ
また、3歳頃からは、絵本だけでなく、文章が多めの児童向けの短編本の読み聞かせを始めました。
最初に取り入れたのは、短編形式で一話完結の物語が楽しめる本。たとえば、『スーパーセレクト100 考える力を育てるお話 ハンディ版 名作や伝記から自然のふしぎまで』(PHP研究所)は、コンパクトで持ち運びにも便利。1話1〜2ページ程度と短いため、飽きずに聞けるのが魅力でした。一つ一つのお話にクイズがついているため、ただ聞くだけでなく考えながら楽しむ“参加型”の読書時間になりました。
『スーパーセレクト100 考える力を育てるお話 ハンディ版 名作や伝記から自然のふしぎまで』(PHP研究所)
4歳頃になると、『シートン動物記』『エルマーの冒険』など長編物語の読み聞かせも楽しめるように。ページ数の多い物語も楽しめるように。字が小さく、文章も長くなると「まだ早いのでは?」と思われるかもしれません。でも、これまでの読み聞かせで文章を耳から聞いて想像する力が育っていたため、長編でもお話の世界にしっかり入り込めるようになっていきました。
もちろん、絵本の読み聞かせも並行して続けていました。ただ、それに加えて“絵が少なくても、自分でイメージできるから面白い”という体験を重ねたことで、子ども自身が絵のない児童書を本棚から持ってくるようになり、「これ読んで」と言ってくる機会も増えました。
児童書の読み聞かせは、“一人読み”へのスムーズなステップにもなります。絵に頼らず、活字から情景を描く力を少しずつ育てていく。そんな積み重ねが、子どもの読書世界を大きく広げてくれました。
読書好きにする読み聞かせのコツ④ 一人で黙読へ
児童書の読み聞かせを始めた3〜4歳頃、特にひらがなを教えたわけではなかったのですが、絵本の読み聞かせを通じて自然に文字に親しみ、自分で読めるようになっていきました。あるとき、静かに本を眺めていると思ったら、しっかり内容を理解していて驚かされたことをよく覚えています。そこから徐々に、親が読み聞かせをしなくても、自分の力で絵本や児童書を読むように。
最初に“自分で読む”対象になったのは、絵が豊富で文字が大きく、ルビ(ふりがな)の付いた児童書でした。特に役立ったのが以下のようなシリーズです。
「よみとく10分シリーズ」では、科学の話や歴史上の人物の伝記などに興味を持ち、小学校入学前後には、対象学年が6年生向けの巻まで読むほどに。内容が少し難しくても、1話完結の短編形式で読みやすく、興味関心を引き出してくれる構成が、読書意欲を大きく後押ししてくれました。
小学校に入る頃には、自然と文庫サイズの本も読めるようになっており、今では毎日学校の図書室に通って本を借りるのが日課に。『放課後ミステリークラブ』(WILLこども知育研究所)、角川つばさ文庫『気まぐれロボット』、青い鳥文庫『しっぽをなくしたイルカ』など、ジャンルを問わずさまざまな本を次々と読んでいます。1冊を30分ほどで読み切ってしまうこともあり、読み進めるスピードも格段に上がりました。
とはいえ、“絵本卒業”というわけではありません。今でも絵本は大好きで、図書館では児童書や学習まんがとあわせて、自分で絵本を選んで楽しんでいます。「絵が多いから簡単な本」ではなく、「好きだから読む本」。そんな自由な選び方を尊重することで、“本を読むことそのもの”が日常に根付いていくのだと感じています。
まとめ:主体的に、自由に。本の世界を旅してほしい
「どんな本を、どんなふうに読むか」は子ども自身が決めること。わが家では、親が「この本を読ませたい」と決めるのではなく、「読んでみたい」という気持ちを尊重するような読み聞かせを心がけてきました。大切なのは、“読まされる”のではなく、“自分から手に取る”という経験の積み重ね。
これからも、興味のままに本を選び、自分のペースで本の世界を旅していってほしい。そんなふうに願いながら、これからもわが家では「読書がそばにある日常」を大切にしていきたいと思います。
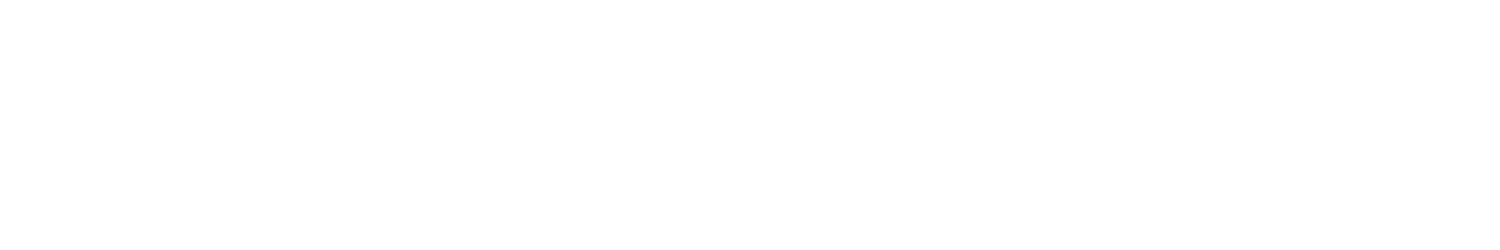




コメント