小学校受験を経験して、「本当にやってよかった」と感じることがたくさんあります。一方で、実際に取り組んでみて初めて気づいた、気をつけたい点もありました。今回は、小学校受験の体験談をもとに、わが家の受験の道のりを振り返りながら、小学校受験のメリット、価値についてお伝えしたいと思います。
子どもが2歳くらいまでは、「のびのびと、自分らしく育ってくれたらそれで十分」と思っており、小学校受験はまったく視野に入れていませんでした。住まいを選ぶ際も、学区の公立小学校の雰囲気や評判を重視し、「ここなら安心して通える」と感じた場所に決めました。
しかし、その後さまざまなことを考え、悩み、調べるうちに、子どもが年中になる春から、私立や国立小学校の受験をゆるやかに意識し始めました。そして実際に受験をし、今は国立小学校に通っています。
そして、小学校受験は、本当にやって良かったと感じています。
「合格すること」がゴールではない。そんな小学校受験のメリットを、これから受験を考えるご家庭にこそ、お伝えできればと思います。
小学校受験体験談:小学校受験のメリット
1. 子どもの成長と親子の絆を感じられる時間だった
わが家にとって小学校受験の期間は、子どもの成長を改めて見つめ直す、かけがえのない時間でした。
共働きのわが家では、生後半年から子どもを保育園に預けており、日々の忙しさの中で「気がつけば、いつの間にか成長している」と感じることが多くありました。
ところが、小学校受験に向けて取り組みを始めてからは、子どもをじっくり観察する機会が一気に増えました。
集団の中での立ち居ふるまいや、一人での過ごし方。どんなことに興味を持ち、何が得意で、何が苦手なのか。何をしているときにどんな表情を見せるのか。そんな姿を見つめる中で、「できなかったことができるようになる瞬間」を間近で見守れることが、親としてとても嬉しく、誇らしい経験になりました。
また、「小学校受験=机に向かって勉強するもの」というイメージとは裏腹に、実際の準備では、自然体験や日常の気づきがとても重視されます。
それまで季節行事や自然に目を向けることは園まかせにしていたわが家も、受験を意識してからは、親子で季節の移ろいや草花に触れ、日々の暮らしの中で学びを楽しむようになりました。まさに「生活そのものが学びになる」感覚を、親子で共有できたと思います。
一つの目標に向かって、親子で力を合わせて取り組むなかで、自然と会話も増え、親子の絆はより深まりました。そして何より、子どもの“真の理解者”としての自覚が、私自身の中にも育っていったと感じています。
逆に言えば、すでに幼児期からスポーツや楽器などに打ち込み、親子で目標を持って取り組んでいるご家庭では、同じような手応えをすでに感じていらっしゃるかもしれません。それほどまでに、小学校受験は「親子で共に歩む時間」が根底にあるのだと思います。

2. 「子育ての軸」を見つめ直す機会に
小学校受験では、子どもに合う学校を見つけるために、さまざまな学校の教育方針を知り、自分たちの家庭の考え方と照らし合わせて検討することになります。また、願書や面接の準備を通して、「家庭で大切にしていること」を言葉で表す機会も多くありました。
「どんな子に育ってほしいのか」「ふだんどんな声かけをしているのか」――。普段はなんとなく頭の片隅にあるだけのことを、じっくりと掘り下げて考える時間になったのです。
わが家では、「どんな社会になっても、自分の力でしっかりと生き抜ける子になってほしい」という思いはもともとありましたが、そのためにどんな軸で子育てをしているのかは、どこか漠然としていました。
小学校受験をきっかけに、これまでの子育てを振り返り、また、さまざまな学校の教育理念に触れる中で、わが家が大切にしてきたのは「知・徳・体」のバランスであることに気づかされました。
実際、小学校受験の試験内容は、この「知(思考力)」「徳(想像力・行動力)」「体(体力)」の発達をバランスよく確認するものが多くあります。
たとえば、筆記や運動の試験では知と体が問われ、行動観察では、自分の考えを持ちながら、周囲の人の気持ちに配慮し、臨機応変に動く力(=徳)が求められます。これらはまさに、これからの時代を生きる子どもにとって必要な力そのもの。
わが家にとっては、小学校受験が、幼児期から児童期へと進むタイミングで、子どもの「今の力」を試す成長の節目のように感じられました。
3. 小学校選びは、6年間の学習環境を選ぶこと
小学校受験をするにあたり、さまざまな学校の説明会に参加したり、実際に見学に足を運んだりすることで、小学校の環境をじっくり比較する機会が得られました。
保育園や幼稚園のときも、入園前にはいくつかの園を訪れて、先生の雰囲気や生活の様子、園全体の空気感などを実際に見て選びました。小学校も同じように、それぞれの学校のカラーや教育方針がまったく違うということに気づき、改めて「6年間の学習環境を選ぶ」という視点で学校を見るようになりました。
「子どもに合っているか?」「家庭の教育方針とマッチしているか?」
そんな問いを持って学校を見ることで、単に偏差値や評判ではない、“わが家にとっての良い学校”という考え方が自然と育っていったように思います。
もし、小学校受験に少し関心があるけれど、踏み出すかどうか迷っているという方がいらっしゃれば、まずは「合同説明会」に参加してみるのがおすすめです。複数の学校が一度に出展する場なので、それぞれの先生と直接話すことができ、比較がしやすく、雰囲気の違いが一目でわかります。
私自身も、「受験はちょっと敷居が高いな」と感じていたのですが、合同説明会に気軽に参加してみたことで、一気に視野が開けました。個別の学校説明会では得にくい、俯瞰的な比較ができるのも大きなメリットです。
まずは情報収集のつもりで。気軽な第一歩から、小学校選びの視野がぐっと広がるはずです。
4. 「中学受験ありき」ではない進路の選択肢が見えた
小学校受験を経験したことで、「進路=中学受験ありき」という考え方から少し距離を置いて考えられるようになりました。
特に、内部進学が可能な学校では、中学受験に追われることなく、探究的な学びや自分の好きなことにしっかりと時間を使うことができます。これは、子どもにとってとても大きな可能性だと感じています。
近年の大学入試でも、学力試験だけでなく「総合型選抜」や「推薦入試」など、自分の活動や表現力、意欲などを評価する枠が広がっています。社会に出た後も、単なる知識以上に、熱意・思考力・表現力・主体性・協調性といった力がより重要になってきていると感じます。
だからこそ、もし子どもが何かに興味を持ち、夢中になって取り組み始めたとき、その芽を摘まずに育てていけるような環境があるのは心強い。“受験のための勉強”に忙殺されない進路というのも、選択肢として十分に価値があると実感しました。
そう考えるきっかけのひとつが、漫画『2月の勝者』を読んだことでした。リアルに描かれた中学受験の世界を知り、あらためて「我が子にとっての最適な学びの形とは?」と考えるようになったのです。
特に東京近郊にお住まいの方で、中学受験を視野に入れているご家庭には、ぜひ一度この漫画を読んでみてほしいです。そして、その上で小学校受験という選択肢にも目を向けてみると、新たな気づきがあるかもしれません。
小学校受験体験談:小学校受験のデメリット・気をつけたいこと
1. 「型にはめる教育」にならないよう注意
受験対策塾の中には、「こう聞かれたらこう答える」「このお題にはこういう絵を描く」といった、パターン化された指導が行われる場面もあります。
それぞれの学校が好む子ども像を熟知しているからこそ、「絶対に合格させる」ことを目的とした指導としては理にかなっているのかもしれません。ただ、それに頼りすぎてしまうと、子ども自身の考えや個性を発揮する機会が失われてしまう恐れがあります。たとえそれで合格できたとしても、入学後にギャップを感じて苦しむことになってしまっては、本末転倒です。
本当に大切なのは、「合格のための模範的な表現」ではなく、「その子らしさを伝える表現」だと思います。そのためには、日常の中でその子らしい行動や発言にしっかり目を向け、どこが素敵だったのかを具体的に言葉にして褒めてあげることが、何より大切だと感じました。
2. 金銭的負担はやはり大きい
教室代、模試代、講習代、交通費、そして複数校を受ける場合は受験料や願書提出費用など、想像以上に費用がかかりました。さらに私立小に進学した場合の学費まで考えると、継続的な負担を見据える必要があります。
我が家では結果的に国立小学校に進学したことで、費用面の負担は比較的軽減されました。ですが、準備期間中の出費は決して小さくありませんでした。家庭の経済状況やライフプランと照らし合わせながら、現実的な選択をすることが必要だと感じます。
▶︎関連記事 【共働き家庭の実例】小学校受験にかかった費用を全公開!
まとめ|わが家にとって小学校受験は「してよかった経験」
小学校受験は、子どもの未来のためだけでなく、「家庭全体の価値観を見つめ直す大切な機会」でもありました。確かに大変なことも多いですが、わが家は心から「してよかった」と感じています。
もし迷っている方がいれば、まずは気になる学校の説明会に足を運んでみることをおすすめします。実際に足を運ぶことで、「どんな環境がわが子に合っているのか」を、単なる情報ではなく体感として知ることができるはずです。
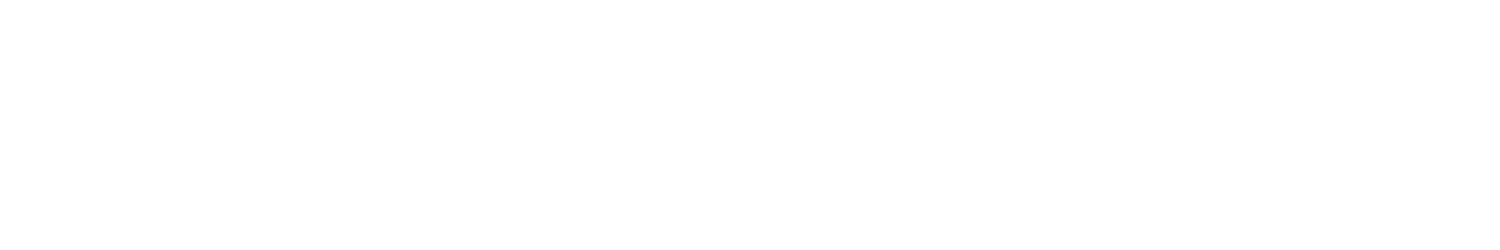




コメント